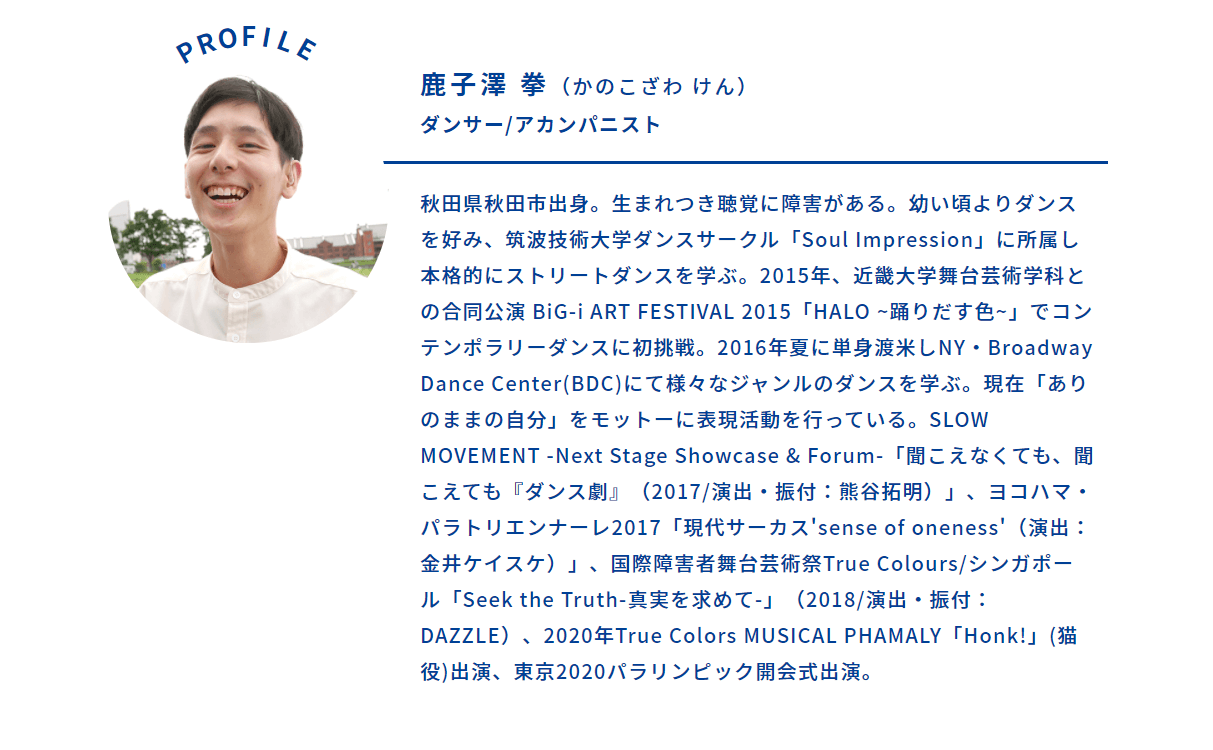NEWS
NPO法人スローレーベルの賛助会員 “SLOW PEOPLE”
こちらにご登録いただいた方は、SLOW LABELの活動に参加しているおひとりお一人の等身大のすがたと変化や気づきを伝えるメディア「その先にあるもの Beyond スロー」の記事をお楽しみいただけます。
今回は、特別に鹿子澤拳さんの記事を丸々公開!
ぜひみなさまお楽しみください。
賛助会員のご登録についてはこちら

今回のbeyond slowに登場するのは、ダンサーの鹿子澤拳さんです。
生まれつき聞こえにくい耳を持つ鹿子澤さんは、パフォーマーとしての経験や、手話言語などを用いたコミュニケーション力を最大限にいかして、SLOW LABELではアカンパニストとして様々に活躍しています。
「言葉を話すのは得意じゃない(笑)」と少し緊張した様子を見せながらも、チャーミングな笑顔が印象的です。
「聞こえないダンサー」って?
「やっぱり手話の表現に頼っちゃうというのもあるし、もともと体で表現する方が得意なんです。『これ!』っていう、しっくりくる日本語が出てこなかったりします。動きがあった方がニュアンスが伝わるというか」

実際にインタビュー中も、体の動きや表情の変化を交えて、臨場感たっぷりに話す鹿子澤さん。もともと幼いころから踊るのが好きだったとのことですが、大学時代はストリートダンスのサークルに所属し、ますますダンスにのめり込みます。一方で「聞こえないダンサー」としての自分の立ち位置について、色々と考えさせられることも増えました。

筑波技術大学ダンスサークル「Soul Impression」のみんなと
「メディアで取り上げられるようになって、『何で聞こえないって言い切ってんの? 補聴器で音楽も聞こえてるじゃん』と言われたりしました。『たしかに。言い返せないな』とも思いましたが、そもそも物心つく前から踊るのが大好きで、『聞こえないとは?』みたいに考える前から踊ってたし、と悩みました」

そんな「言語化できないモヤモヤ」を表現にぶつけたのがミュージカル『レ・ミゼラブル』の名曲『民衆の歌』を、あえて批判も多い「手話歌」という手法を用いた作品なのですが、その話については改めて伺うことにしたいと思います。ともあれ、悩みを抱えながらも、ある芸術系の大学教授から絶賛されたことをきっかけに、鹿子澤さんは芸術表現の道を進む決意をします。
ブロードウェイで感じた「キラキラ」
「『君のダンスいいね!アメリカに行くべきだよ!』みたいに言ってもらえて。そしたら本当にその年にニューヨークに行くことになったんですよ。2週間の短期留学ですが、ブロードウェイでダンスを勉強しました。アメリカはやっぱり進んでいると言っていいのか、個人を個人として見てくれる感じがありました」

本場ニューヨークのブロードウェイダンスセンターでのレッスン
「聞こえないダンサー」としてではなく、一人の人間「鹿子澤拳(かのけん)」として見られることは、鹿子澤さんに表現者としての大きな勇気を与えたようです。昨今のブロードウェイが、人種差別や性差別など、様々な観点からマイノリティ側に立つ傑作を多く生み出していることとも関係があるかもしれません。

「ブロードウェイは、『自分が自分でいいんだと思ってもいいのかな』と思わせてくれた場でした。こういうのを『キラキラ』って言うんだ!って。役者さんひとりひとりがとても輝いていて自分もこういう風になりたい、舞台で表現する人として生きていこうかな、って。それで帰国してすぐ、親に『就活しないわー』と話しました。親も『いいんじゃない?』って」
子どもを信頼して理解している様子が伝わってくるエピソードですが、小学生のころは鹿子澤さんからみて「はあ!?」と思わせる一面もあったようです。
「いわゆる普通学校に通っていたんですが、耳が聞こえないことでからかわれることがありました。それが嫌だと、親に打ち明けたときのお母さんの反応が『よかったー、けんちゃん!』で(笑)。お母さん的には、社会にはとてもシビアな面もあるから、小さいうちに経験できてよかったということだったらしいんですけど。こっちは勇気を出して相談したのに何なの!って感じでした(笑)」


お母さんとの仲良し2ショット
モーニング娘。で踊った幼少期
「かのけん」の愛称で親しまれている、SLOW LABELのアカンパニスト鹿子澤拳さん。今回はダンサーとしてのキャリアを歩み始める前の、幼少期のころについて伺います。生まれつき耳が聞こえにくい鹿子澤さんですが、補聴器を着ければ口語での日常会話も可能です。実際にどれくらいの音が聞こえるのでしょうか。
「数値的には、補聴器を着けて一番聞こえる音域で40デシベルの音くらいまで聞こえるレベル(平均60dBほど)。だからこうやって会話もできますが、補聴器を外すとまったく聞こえない。というか、駅のアナウンスとか聞き慣れているものだと、何か音が流れているのは分かるという感じ。内容までは聞き取れませんね」

デシベルは音の大きさの単位で、鹿子澤さんの場合は40デシベル以下の音は補聴器ありでも聞こえにくいことになります。日常会話の音量は60デシベル程度だそうですが、ささやき声となると30デシベルほどになってしまうとのことなので、どれくらいの音が聞こえるのか何となく想像していただけるでしょうか。
「小学生のころ、聞こえないことでからかわれたと言いましたが、それが基本的に男子からだったんですね。いじめというほどではなかったけど、その影響もあって、今でも同年代の聞こえる男性にちょっと苦手意識あったりしますね。どっちかというと女の子と遊ぶことが多く、モーニング娘。とか流行っていた時代だったので、一緒に音楽かけて踊ったりしている子でした」
小学生時代は、いわゆる普通学校(インテグレーション教育)に通っていましたが、中学校はろう学校を選択します。しかし同級生の会話や授業は、鹿子澤さんがそれまで使ったことのない手話が中心。発話を伴う手話だったのがせめてもの救いですが、会話の内容が高度になるとついていけません。

聞こえないことが嫌になった時期も
「『このやろー!』と思って、頑張って半年くらいで覚えたんですけど(笑)。でもその後、高校に入って、今度は手話もちゃんと分かるし会話についていけないことはないだろうと思ってたら、都会だからなのか、手話が速いんですよね。また『このやろー!』って勉強して。でも、そのおかげで手話っていつからあるんだろうとか、色々考えるようになって手話が好きになりました」

学生時代、手話で仲間と会話をする鹿子澤さん
鹿子澤さんは秋田県秋田市の出身です。「あくまで個人の体感です(笑)」と前置きしつつ「手話もゆっくりだった」という、のどかな故郷を離れ、都会の高校を目指す理由には少し切ない思いがありました。

「秋田だと、やっぱり聞こえない人の絶対数が少ないんですよね。ひとりで通学しているとき、ふと周りを見たら自転車に乗りながらでも会話していたり、電車で横並びに座ってお互い顔を見ないでも会話が成立していたり。『これが普通なのかな、自分は聞こえない人なんだな』と改めて感じて、すごく胸がキューンとなって。聞こえないことが嫌になった時期もありました」
それならば「聞こえない人がいっぱいいるところに行けばいい」と受験したのが、筑波大学附属 聴覚特別支援学校(通称「筑波ろう学校」)という全国からも聞こえない人が多く集まってくる国立学校です。
「そのときも親は特に反対しなくて、『あなたに合格できる学力があればの話ですけど(笑)』みたいな。『はあ!?』とか思って勉強したんですけど(笑)」

恵まれていたのは、気づかせてくれる友達がいたこと
SLOW LABELでアカンパニストを務める、ダンサーの鹿子澤拳さん。大学進学後は、ストリートダンスのサークルに所属し、本格的にダンス表現に取り組んでいきます。そのなかで生まれたのが連載1回目で紹介した、『レ・ミゼラブル』の『民衆の歌』です。
「筑波技術大学という、視覚障害の方や聴覚障害の方が集まる大学に行っていました。そこで所属していたのが、日本でも一つしかない、全員が耳が聞こえないという珍しいダンスサークルだったんです。そういうこともあってメディアでもよく取り上げられていました」

学園祭で披露した「手話歌」でのレ・ミゼラブルの「民衆の歌」
もともとダンスが好きで踊っている鹿子澤さんの意志とは関係なく、分かりやすさを求めるメディアが「聞こえないダンサー」として紹介することは、同じ「聞こえない人たち」からの反発も呼びました。先に触れた、補聴器を着けて聴覚活用しているのに「聞こえない」と言い切ることに対する批判もその一例です。
「『テレビ見たよ、すごいね!』と言ってくれる人もいたんですが、僕が恵まれていたのは、ちゃんとつっこみしてくれる友達がいたことです。はっと気づかせてくれる。『自分の子どもも補聴器着けて発話練習しさえすればテレビで踊るかのけんみたいになれる、と親御さんが安易に思ってしまうのが一番怖い』と言ってくれた同級生もいたんです」

「聞こえない」の状況は人それぞれ。努力すれば必ず聴力が改善するという思い込みは、大きな危険性をはらんでいます。また、耳が聞こえないことそのものが劣っているという価値観にも繋がりかねません。日本語と異なる一つの独立した言語である日本手話を話すことは、「ろう者」のアイデンティティにとってとても大切なことです。

「戦う者の歌が聴こえるか」という歌詞
「自分もろう学校での生活で、ろう文化というものを知りました。ろう学校で何気なく先生たちがしていたこと、たとえば生徒を呼ぶときに電気をつけたり消したりするのとか、あれもこれもろう文化だったんだ!って。ろう文化、めっちゃいいじゃん、好きだなって。でも、自分がろう文化を突き進んでいいのかな?簡単に好きとか言っちゃっていいのかな?という迷いもあります」

聞こえる親のもと日本語環境で育った鹿子澤さんの場合、ろう文化はあくまで獲得したもの(デフコミュニティに属するひとり)。家族みんなが聞こえないデフファミリーで育ったネイティブではないという葛藤もあるようです。でも健聴者と同じように聞こえるわけでもない。自分の立ち位置について思い悩んでいたときに発表した作品が、先に触れた『民衆の歌』の手話歌です。
「『レ・ミゼラブル』はフランス革命のころの話で、様々な社会の壁があったと思うんです。友人に勧められて初めて観たとき、この民衆のなかに自分がいてもいいんじゃないかなって感じて。『戦う者の歌が聴こえるか』という歌詞があるんですけど、聞こえる人と聞こえない人のあいだの壁だけじゃなくて、僕自身はまさかの当事者のなかでの壁にもぶちあたっていたというか。この気持ちをどこにぶつけたらいいんだろうって」

たどり着いた「かのけんはかのけん」
「かのけん」こと鹿子澤拳さん。SLOW LABELではアカンパニストとして、また2020年『ヨコハマ・パラトリエンナーレ』のプログラム『パラトリテレビ』ではディレクターとしても活躍しました。「聞こえないダンサー」として紹介されることから生まれた違和感について考えるため、色々な聞こえない人の話を聞くようになったといいます。
「友人たちとも意見の交換というか、そういう時間をたくさん作るようになりました。以前は気にせず『ともだちー!』って感じだったんですけど(笑)。自分でも発言する前に少し立ち止まって考えることが増えました」

言葉ひとつとっても「難聴」「聴覚障害者」「ろう者」などあり、その定義も一見複雑です。「ろう者」を自認する人には、手話言語を使うことを誇りに思い、聞こえないことを肯定的に捉える傾向があるそうです。
「そういう意味では僕は難聴というべきなのかも。手話がまだ『手真似』とか呼ばれ、今よりひどい差別があったころから、本当に聞こえない人たちが大事にしてきたのがろう文化で、僕たち難聴はそれを後から学んできたというか。ろう学校での生活を経てろう文化にふれ、そしてろう文化を好きになった。そこから自分はろう者だと思うようになった。でも少し聞こえる(聴活活用をしている)自分がろう者を名乗ってもいいのか、だったら聴覚障害者かというと『聞こえないことは障害じゃない』って。すごく悩んで『もういいや、僕はかのけん!』って。僕は僕なんだって割り切りました。周りも『かのけんはかのけん』ってわりと納得してるみたいです(笑)」

考えに考えた末にたどり着いた答えは、ブロードウェイでも感じた「自分は自分でいい」という感覚でした。また、鹿子澤拳さんの世代は、技術の進歩という意味で大きく変化があった時代に生まれた世代でもあり、今後ますます多様な個性を持つ「聞こえない人」が現れてくるかもしれません。
「今は新生児段階で分かることもありますが、僕らの世代は2歳くらいになって『〇〇ちゃんー』って読んでも反応がなくておかしいな?と病院に行って初めて分かる感じです。僕はたまたま別の深刻な病気があって、大きな病院で精密検査を受けて発覚したので、学会レベルの珍しいタイプだったみたいです。お母さんが『けんちゃん論文に載ってるよ!』って(笑)。北海道で人工内耳の手術を受けたのも僕の同期が最初でした」

頭部に電極を埋め込むことで、電気信号に変換した音声の情報を脳に伝える人工内耳は、ますます多くの人に使われていっています。人工内耳を使用しても、電話での会話や、メロディの聞き分けが難しい、そもそもあまり適合せず聞こえにくいままの人もいるなど、人によっても様々だそうです。また、順応するのに訓練が必要なため、できるだけ小さいうちに手術することが推奨されています。意思決定権を持てないうちの大きな決断という点からも多くの意見がありそうです。
「人工内耳を使って聞こえるようになった人が増えても、『聞こえない』ことについて僕と同じようにモヤモヤする人は出てくると思う。自分は『聞こえない人』だから人工内耳を着けてるんだって。そういう人に、ちょっと先に色んなことを知った僕が表現を通じて『あなたはあなたでいいんだよ』と伝えることは何かプラスになるんじゃないかなって。そういう思いで2020年にYouTubeチャンネルも始めました。なかなか更新できないんですけど(笑)」

YouTuberとしての才能は、2020年『ヨコハマ・パラトリエンナーレ2020』のプログラム『パラトリテレビ』でも発揮されました。新型コロナウイルス感染拡大の影響でパラトリエンナーレの規模を縮小するなかで、オンラインで展開する『パラトリテレビ』は重要な一角を担いました。そして、そのディレクターに抜擢されたのが鹿子澤さんでした。

象の鼻テラスでの撮影風景

カメラを覗きながら合図を出す鹿子澤さん
『パラトリテレビ』を振り返って
「テレビや新聞でも障害者を取り上げられることはあるけど、演出をするのは基本的に健常者。そういう大きなメディアとは違う視点で、ありのままのみんなを見てもらおうと考えました。僕が出ないのはちょっと寂しいですが(笑)」

『パラトリテレビ』での経験を振り返って、鹿子澤さんが今思っていることについてコメントを寄せてくれました。
「パラトリテレビに携わってみて、まず率直な感想としてひとつのコンテンツを作るのにこんなにたくさんの方の労力が必要なんだなぁと思いました。どういうコンセプトのもとで、どのようなコーナーを作るか。たくさんの方に見てもらうためにどのような編集方法(テロップの表記方法等)が良いのか、つねに考えながら作業を進めていたのでとある日には頭がパンクしかけたこともありましたが、たくさんの方のご協力のおかげで無事に番組放送までつなげることができました。

「普段自分が舞台に立つ際にも、たくさんの方の思いがあってここに立てていると感謝の気持ちを常に忘れないようにしていますが、パラトリテレビの制作に携わったことで、あらためてその気持ちを大事にしていきたいと思うことができました。」
「そしてパラトリテレビの制作にあたって、またたくさんの方との新たな出会いもありました。自分が考えたことのない新たな価値観に触れることもできましたし、より視野を広げられたとても貴重な機会となりました。何より充実したコンテンツ(撮影データ)を編集している時間が一番楽しかったです。本当にありがとうございました。」

「今後のかのけんの活動として、上にも述べたように、色々な思いから悩んでいる人々に「あなたらしく生きていい」ということを伝えていきたいです。そのためには引き続きどんどん色々なことにチャレンジしていきたいし、「ありのままの自分らしく」を忘れずに様々な舞台で表現活動をおこなっていきたいと思っています」


お読みいただきありがとうございました